
扁平足の評価って見た目だけ?
どうやって評価するの?

扁平足を数値で表せる?
「扁平足で困っている」という人は意外と少なく、扁平足を治療のメインターゲットにする機会は少ないかもしれません。
ですが、扁平足=足アーチの破綻は,下肢全般の疼痛や支持性低下によるパフォーマンス低下を引き起こします。
そのため、扁平足を評価することは全身の治療に関わる重要な要素です。
この記事では、扁平足の解剖学的な状態と扁平足を簡単に評価できる3つの方法について論文などのエビデンスをもとに解説します。
扁平足の評価を知ることは、状態の変化や臨床での効果判定にも重要です。
この記事の結論は以下の通りです。
- 扁平足とは、内側縦アーチが破綻して後足部が回内、前足部が外転回外した状態
- 扁平足では、足部や膝を中心とした下肢の疼痛や疲労、パフォーマンス低下を引き起こす
- 扁平足のおススメ評価は、too many toes test、leg heel alignment、舟状骨落下テストの3つ
- 扁平足の解剖学的な特徴がわかる
- 扁平足の簡単に数値で評価する方法がわかる
- 扁平足に対する運動アプローチがわかる
扁平足への運動療法については別の記事にてまとめています。
扁平足の解剖学的な特徴と影響
ここでは、扁平足の解剖学的な特徴と扁平足の影響をまとめて紹介します。
結論は以下の通りです。
- 扁平足とは、内側縦アーチが破綻して後足部が回内、前足部が外転回外した変形
- 扁平足では、距骨下関節回内,距骨内旋,踵骨外反,下腿内旋・外方傾斜,舟状骨下方偏位,楔状骨外転が生じる
- 扁平足は足部や膝関節を中心とした下肢の疼痛、疲労感、パフォーマンスの低下に影響する
足内側縦アーチの解剖学的構造
扁平足に重要な内側縦アーチの解剖学的な構造を解説します。
結論は以下の通りです。
- 内側縦アーチを構成する骨:踵骨ー距骨ー舟状骨ー内側楔上骨ー第1中足骨 その中でも舟状骨は重要
- 内側縦アーチを構成する筋:後脛骨筋、前脛骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋、母趾外転筋
- 後脛骨筋は内側縦アーチの保持に重要
足の内側縦アーチは、足の重要な構造的特徴の1つで”土踏まず”を形成しています。
内側縦アーチは、衝撃の吸収、体重の伝達、歩行時の推進力など足の機能として重要です。
内側縦アーチは骨、靭帯、筋で構成され、いかのようになっています。
- 骨:踵骨ー距骨ー舟状骨ー内側楔上骨ー第1中足骨
- 靭帯:底側踵舟靭帯,距踵靭帯,楔舟靭帯,足根中足靭帯など
- 筋:後脛骨筋 舟状骨を上方へ引く
- 前脛骨筋 第1中足骨底を引く
- 長母趾屈筋および長趾屈筋 第1~5趾を引き距骨と踵骨を安定させる
- 母趾外転筋 第1中足骨と距骨を引く

骨、靭帯、筋によって内側縦アーチを静的・動的に維持できるように支えています。
内側縦アーチでは、特に舟状骨がkey stoneと呼ばれ、アーチを形作るため重要です。
また、舟状骨を上方へ引き上げる役割がある後脛骨筋も大切です。
扁平足の解剖学的な特徴
扁平足が解剖学的にどんな状態となっているか解説します。
- 扁平足は足の内側縦アーチが消失して土踏まずが消失した足部変形の総称
- 内側縦アーチの消失=後足部が回内し,前足部が外転回外
- 内側縦アーチの消失=距骨下関節回内,距骨内旋,踵骨外反,下腿内旋・外方傾斜,舟状骨下方偏位,楔状骨外転

扁平足は内側縦アーチが消失した足部変形の総称です。
内側縦アーチが消失すると、運動連鎖や荷重を支えるために足部の骨はさまざまな変位が生じます。
- 距骨下関節回内
- 距骨内旋
- 踵骨外反
- 下腿内旋・外方傾斜
- 舟状骨下方偏位 ・楔状骨外転
これらを足全体でみると、後足部の回内・前足部の外転回外として現れます。
ちなみに、内側縦アーチが消失する要因はさまざまです。
一般的な例を以下に挙げます。
- 後脛骨筋の機能不全
- 足筋の筋緊張低下
- 靭帯の緊張低下
- 肥満
- ケガの既往
- ステロイドの使用
アーチが消失する大きな要因として、筋や靭帯によって体重が支えられなくなることが挙げられます。
扁平足による疼痛やパフォーマンスへの影響
扁平足では身体にどのような影響があるか解説します。
扁平足は、足部や膝関節を中心とした下肢の疼痛、疲労感、パフォーマンス低下を引き起こす
扁平足は内側縦アーチの消失により、足部の支持性や足底機能の低下から身体へ多くの影響がでます。
- 疼痛:足底腱膜への持続的な伸張ストレスが加わり,足底腱膜炎や足底の疼痛(足底腱膜付着部痛) を誘発する.また、膝関節など下肢の広範囲の痛みに関係する
- 疲労感:底側踵舟靱帯や長足底靱帯,後脛骨筋を始めとする靱帯や筋に負荷が増加し,その起始部や周囲に痛みや疲れが生じやすい.
- パフォーマンス低下:足底のスプリング機能が低下し,足部の蹴り出し等のパフォーマンスが低下する.

興味深い研究として、扁平足が体幹筋の持久力と関係することが報告されています。
Elataarらは扁平足群と対照群で体幹筋の持久力を比較しました。
結果は以下の通りです。
- 体幹屈筋と体幹伸筋の持久時間は,扁平足群と対照群で有意差を認めなかった(p>0.05)
- 体幹側屈筋の持久時間は、扁平足群の方が有意に低かった(p<0.001)

扁平足患者の方が、体幹側屈筋の持久力が低いことを明らかにしています。
ちなみに、扁平足で体幹側屈筋の持久力が低かった要因を以下のように考察しています。
内側縦アーチ消失は衝撃吸収能力とバランス感覚が低下し,安定性の低下により持久力が低下する可能性
扁平足による股関節外転筋の筋力低下を補うため体幹外側筋が過活動により筋疲労を起こす可能性
扁平足は支持性やバランス能力の低下から立位・歩行を中心として、スポーツや日常生活へ影響します。
足部変形の影響に気がつくことも臨床では重要ですね。
扁平足を簡単に数値で評価するおススメ評価3選
ここからは、扁平足を簡単に評価できるおススメの評価スケールを3つ解説します。
- too many toes testは、2趾(第4~5趾)以上が見えたら扁平足の前足部外転と判定
- leg heel alignment(LHA)は、7°以上は扁平足の距骨下関節回内・下腿外方傾斜と判定
- 舟状骨落下テスト(Navicular Drop Test: NDT)は、10mm以上で扁平足・内側縦アーチの消失と判定
too many toe sign
扁平足による前足部の外転を評価する”too many toes test”を解説します。
評価方法:安静立位姿勢を指示して、後から足趾の数を観察する
判定:(正常)第5趾と第4趾の一部しかみえない
(陽性)多くの足趾(2趾以上)がみえる


内側縦アーチの消失すると、前足部は外転します。
そのため、後方から観察すると足趾が多くみえます。
too many toes signでは、第4趾(2足趾以上)みえると扁平足による前足部の外転であると判断できます。
- 短時間で判定できる
- わかりやすく、被験者の負担がない
- 計測に道具がいらない
too many toes signは簡単に扁平足を評価できる測定方法の一つです。
是非臨床でも活用してみましょう。
leg heel alignment(LHA)
扁平足による後足部の回内や下腿の外方傾斜を評価する”leg heel alignment(LHA)”を解説します。
評価方法:下腿(下腿遠位1/3の中点-アキレス腱付着部中央を結ぶ線)と踵骨(踵骨下端中央-アキレス腱付着部中央を結ぶ線)のなす角を測定する
判定:LHA ≥ 7°は距骨下関節の回内と下腿の外方傾斜が増加している


内側縦アーチが消失すると、足部は代償として後足部(距骨下関節)の回内や下腿の外方傾斜が生じます。
そのため、下腿軸と踵骨軸のなす角は増加します。
Leg heel alignmentを用いた研究はいくつかあり、以下のような報告があります。
- 正常値は3.5~7.0° (Sobel, 1999)
- 慢性足関節不安定症の無症候群6.1±3.3°,有症候群8.7±3.2° (Maeda, 2023)
- LHA7°以上を後足部外反群と定義 (Fujishita, 2023)
- 正常範囲3~5° (工藤,2017)
LHAの基準値はいくつか報告されていますが、
7°以上だと扁平足による距骨下関節の回内・下腿の外方傾斜が増加している状態と判断できます。
また、評価の信頼性についてはJonsonらにより報告されており、級内相関系数ICC0.88と比較的に高い信頼性を示す評価です。
- 短時間で判定できる
- わかりやすく、被験者の負担がない
- ゴニオメーターがあれば計測可能
- 数値で示せるため経過の評価もできる
Leg heel alignmentの測定では、下腿軸と踵骨軸の確認が難しく感じるかもしれませんが、慣れれば簡単です。
短時間で数値で評価できるため、治療効果や変化をみやすい扁平足の評価です。
舟状骨落下試験(Navicular Drop Test: NDT)
内側縦アーチに最も重要な舟状骨の高さを評価する” 舟状骨落下テスト(Navicular Drop Test: NDT)”を解説します。
舟状骨落下テストは扁平足を判定する最もスタンダードな評価方法の一つです。
評価方法:①椅子座位で床から舟状骨結節までの高さ(mm)を計測
②立位で床から舟状骨結節までの高さ(mm)を計測
③座位と立位の高さの差がスコア
判定:座位と立位の差が10mm以上は舟状骨落下・扁平足


舟状骨は内側縦アーチを形成する重要な骨であり、舟状骨が落下すると内側縦アーチは消失します。
そのため、非荷重時と比べて荷重時の舟状骨の高さが保たれていれば、内側縦アーチが機能している状態。
非荷重時に比べて、荷重時に舟状骨が10mm以上、下がれば扁平足と判断します。
舟状骨落下テストによって扁平足を定義する研究はいくつかあります。
- 10mm以上は扁平足 (Aenumulapalli, 2017)
- 10mm以上は舟状骨落下が陽性 (Elsayed, 2023)
- 正常範囲 <10mm (工藤,2017)
非荷重によりも荷重時に舟状骨が10mm以上、下がっていれば、内側縦アーチの消失・扁平足と定義しているようです。
また、舟状骨落下テストの信頼性はDengらにより報告されており、級内相関系数ICC0.83~0.95と高い信頼性が報告されています。
- 扁平足のスタンダード評価
- わかりやすく、短時間で判定できる
- メジャーがあれば計測可能
- 数値で示せるため経過や治療効果の評価ができる
舟状骨落下テストは、治療効果の判定にも用いられることが多く、扁平足のゴールドスタンダードの評価の一つです。
舟状骨の触診や舟状骨結節の同定は難しく感じるかもしれませんが、
骨の配置をイメージして経験を積むことで容易になっていきます。
扁平足の変化を評価するためにも活用してみましょう。
まとめ
ここまで、扁平足の解剖学的な状態や判定、扁平足のおススメ評価を解説しました。
- 扁平足とは、内側縦アーチが破綻して後足部が回内、前足部が外転回外した変形
- 扁平足では、距骨下関節回内,距骨内旋,踵骨外反,下腿内旋・外方傾斜,舟状骨下方偏位,楔状骨外転が生じる
- 扁平足は、足部や膝関節を中心とした下肢の疼痛、疲労感、パフォーマンス低下を引き起こす
- too many toes testは、安静立位姿勢を指示して,後から足趾の数を観察する評価
- too many toes testは、2趾(第4~5趾)以上が見えたら扁平足の前足部外転と判定
- leg heel alignment(LHA)は、下腿軸と踵骨軸のなす角を評価
- leg heel alignment(LHA)は、7°以上は扁平足の距骨下関節回内・下腿外方傾斜と判定
- 舟状骨落下テスト(Navicular Drop Test)は、荷重位と非荷重位で床から舟状骨の高さを比較する評価
- 舟状骨落下テスト(Navicular Drop Test)は、荷重位と非荷重位の差が10mm以上で扁平足・内側縦アーチの消失と判定
- 3つのテストは、短時間で簡単に測定でき、数値から変化を評価することもできる
おススメの運動アプローチ3選
- 足関節背屈のストレッチ
- 後脛骨筋の筋力強化練習
- 足趾屈曲運動
足関節背屈のストレッチ
方法:通称“アキレス腱のばし”で有名なストレッチですね.膝関節伸展位と屈曲位の両方で伸ばした方がよく,目安は30秒×3セットです.
解説:足関節の背屈制限が生じると,後脛骨筋腱や長短腓骨筋腱に伸張ストレスが増強します.また,荷重位での下腿前傾運動時(歩行など)に足部回内が増強するため,回外に作用する後脛骨筋に伸張ストレスがかかり,扁平足を誘発します.
足関節背屈のストレッチにより足関節背屈制限の改善を図ります.
ちなみに,膝屈曲位での足背屈制限では,ヒラメ筋や長母趾屈筋,長趾屈筋,短腓骨筋などの関与が疑われます.
特に長母趾屈筋は下腿後面で距腿関節の後方を通るため,距骨の後方滑り運動を阻害しやすいので注意が必要です.
後脛骨筋の筋力強化練習

方法:内果の後方でボールを挟み,踵上げ運動を行う.
解説:後脛骨筋は骨間膜後面から舟状骨に停止する筋で,内側アーチを形成する重要な筋です.
そのため,加齢などをきっかけに後脛骨筋の機能不全や収縮不全が生じると,舟状骨は下制し内側縦アーチは破綻します.
内果でボールを挟む踵上げは,後脛骨筋に特異的に負荷をかけることができ,内側縦アーチを保つために有用です.
足趾屈曲運動

方法:座位にて足趾でグーを作ります.うまく出来なくても続けると少しずつ曲がるようになります.
解説:日本整形外科学会も扁平足の治療として紹介しており,足趾の屈曲運動は足底筋の筋収縮,筋力強化を図り,アーチを安定させます.
これも有名なアプローチの一つだと思いますが,どこでも手軽に実施できる点もおススメな理由です.
参考資料
- H A Jacob. Forces acting in the forefoot during normal gait–an estimate. Clin Biomech (Bristol). 2001.
- 中村隆一,他.基礎運動学第6版.医歯薬出版株式会社.
- 青木治人,清水邦明.スポーツリハビリテーションの臨床.
- Negin Soltani, et al. Flatfoot Deformity; Exercise to Therapeutic Interventions: A Systematic Review. Iran J Public Health. 2024.
- 大塚礼,他.地域在住高齢者における扁平足と脚の自覚症状,および肥満との関連.日本公衆衛生誌.2003.
- Negin Soltani, et al. Flatfoot Deformity; Exercise to Therapeutic Interventions: A Systematic Review. Iran J Public Health. 2024.
- McPoil TG, et al. Evaluation and management of foot and ankle disorders: present problems and future directions. J Orthop Sports Phys Ther.1995.・JL Riskowski, et al. Associations of Foot Posture and Function to Lower Extremity Pain: The Framingham Foot Study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013.
- Faten F Elataar, et al. Core muscles’ endurance in flexible flatfeet: A cross – sectional study. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2020.
- Ettore Vulcano, et al. Approach and treatment of the adult acquired flatfoot deformity. Curr Rev Musculoskelet Med. 2013.
- Jensen K Henry, et al. Adult-Acquired Flatfoot Deformity. Foot Ankle Orthop. 2019.
- Rajwinder S Deu, et al. Tendinopathies of the Foot and Ankle. Am Fam Physician. 2022.
- Preet Singh Bubra, et al. Posterior tibial tendon dysfunction: an overlooked cause of foot deformity. J Family Med Prim Care. 2015.
- S R Jonson, et al. Intraexaminer reliability, interexaminer reliability, and mean values for nine lower extremity skeletal measures in healthy naval midshipmen. JOSPT. 1997.
- E Sobel, et al. Natural history of the rearfoot angle: preliminary values in 150 children. Foot Ankle Int. 1999.
- Noriaki Maeda, et al. Relationship of Chronic Ankle Instability With Foot Alignment and Dynamic Postural Stability in Adolescent Competitive Athletes. Orthop J Sports Med. 2023.
- Hironori Fujishita, et al. Effects of Rearfoot Eversion on Foot Plantar Pressure and Spatiotemporal Gait Parameters in Adolescent Athletes. Healthcare (Basel). 2023.
- 工藤慎太郎 編著 運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略.医学書院.
- Juli Deng, et al. Reliability and validity of the sit-to-stand navicular drop test: Do static measures of navicular height relate to the dynamic navicular motion during gait? Journal of student physical therapy research. 2010.
- Ashok Aenumulapalli, et al. Prevalence of Flexible Flat Foot in Adults: A Cross-sectional Study. J Clin Diagn Res. 2017.
- Walaa Elsayed, et al. The combined effect of short foot exercises and orthosis in symptomatic flexible flatfoot: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2023.
- Tanya Brijwasi, et al. A comprehensive exercise program improves foot alignment in people with flexible flat foot: a randomised trial. J Physiother. 2023.
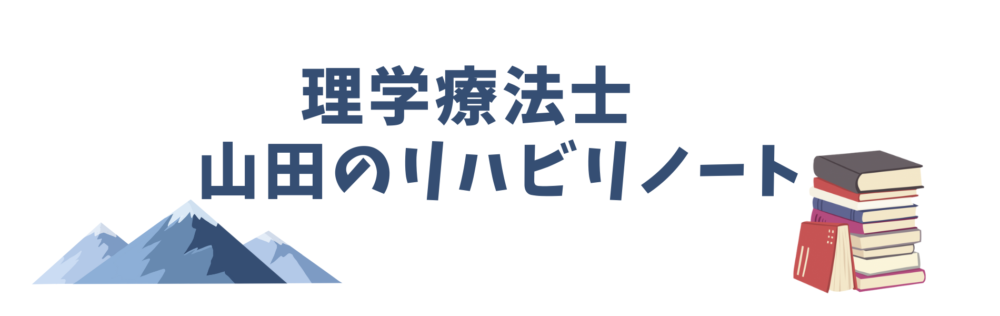


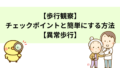
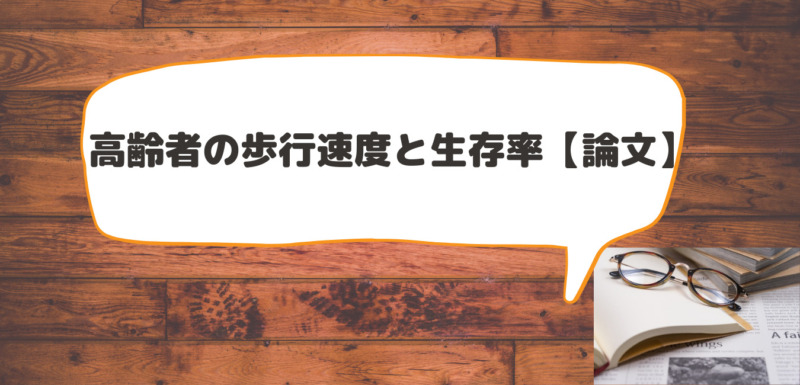
コメント