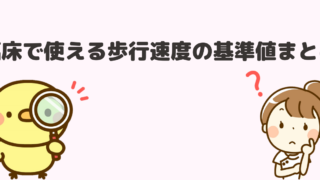 評価
評価 【歩行速度】臨床で使える基準値【まとめ】
歩行速度って,どうやって臨床に活かすの? 歩行能力はセラピストが最も評価する項目の一つです. 今回は通常歩行速度を測定することで,何が読み取れるのかをまとめています. 結論は以下の通りです。 歩行速度<0.8m/secの人は平均余命が短い可...
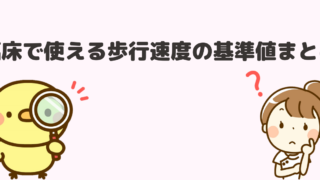 評価
評価 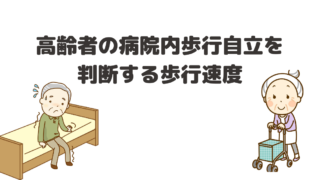 評価
評価 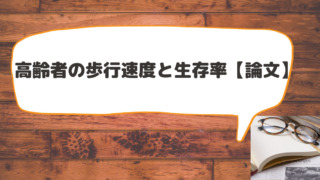 評価
評価  評価
評価 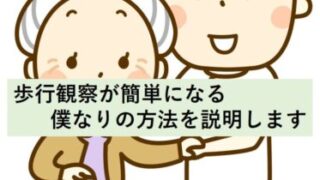 評価
評価 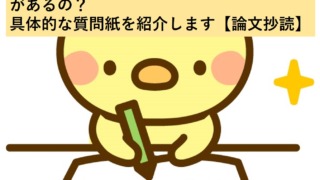 評価
評価 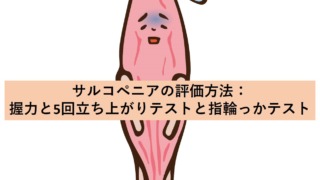 評価
評価 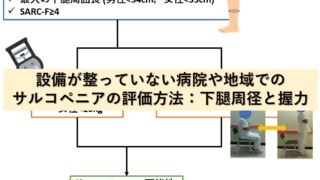 評価
評価  評価
評価  高齢者
高齢者