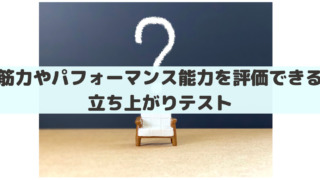 評価
評価 【立ち上がりテスト】筋力やパフォーマンス能力の目安【身体機能評価】
MMTでは上がってるけど、どれくらい運動できるの?MMTの筋力評価だけでは、スポーツ時に十分な筋力か判断できない!MMTはリハビリでよく用いられる評価ですが、パフォーマンスにおける筋力の程度を評価したい際は、限界を感じることがあります。BI...
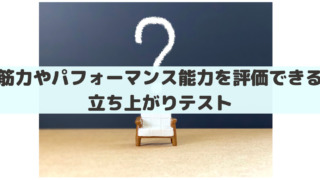 評価
評価  運動療法
運動療法  評価
評価 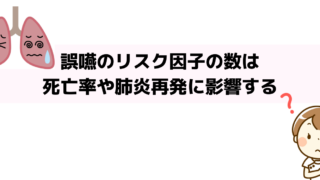 リハ栄養
リハ栄養 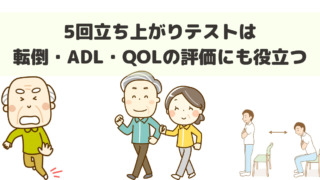 評価
評価 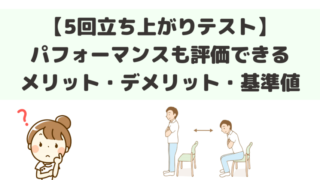 評価
評価 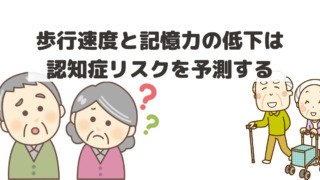 評価
評価 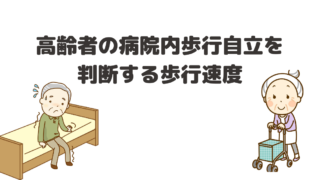 評価
評価 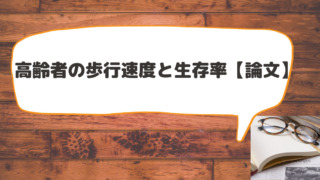 評価
評価 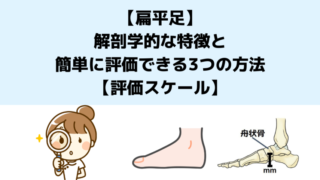 評価
評価