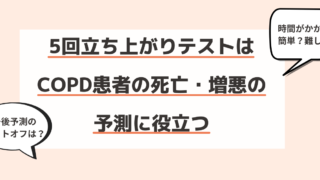 評価
評価 【COPD】死亡・増悪リスクを予測するカットオフ値【5回立ち上がりテスト】
COPD患者さんに、6分間歩行テストをするのは患者さんの身体負担が大きく、時間的にも難しい。COPDの予後を検討する5回立ち上がりテストのカットオフ値は?身体機能はCOPD患者の予後と関係していると報告はいくつかあり、リハビリでの身体機能測...
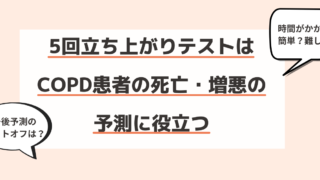 評価
評価 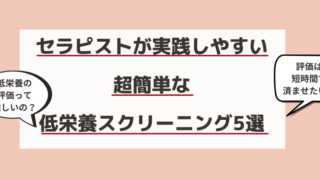 評価
評価 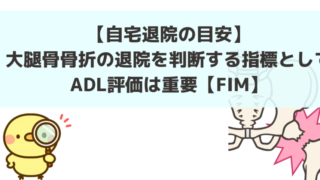 評価
評価 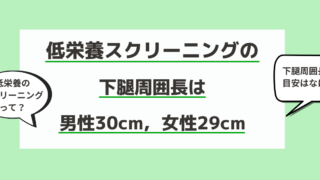 評価
評価  評価
評価 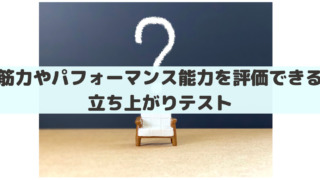 評価
評価  評価
評価 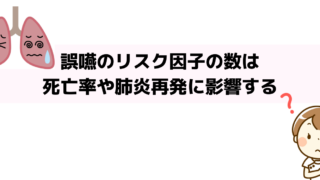 評価
評価 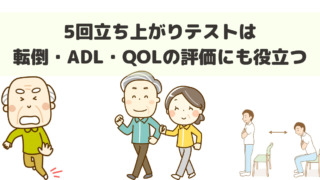 評価
評価 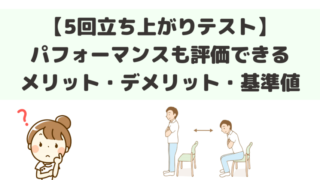 評価
評価